クレーム対応・カスタマーハラスメント対策トピックス
総合研究部 専門研究員 森田 久雄
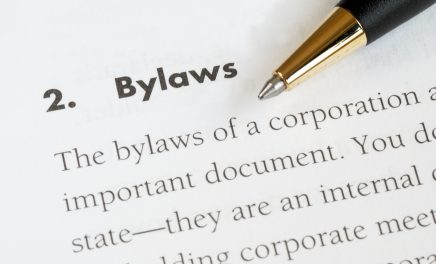
条例施行後の動向
ご存じの通り、本年4月1日より「カスタマー・ハラスメント防止条例」が北海道、東京都、群馬県、三重県桑名市で施行されました。これ以外の自治体でも、条例制定を目指す動きが多く見られますが、実際に施行された結果はどうなっているでしょうか。もちろん、各企業でカスハラ対策を講じる動きは加速していると感じていますが、条例違反の事例は三重県桑名市以外では、罰則が設けられていないため、明確に違反行為があったとする話題になり難いのが実情です。
当たり前の話ですが、法令・条例の他で様々な規定を設けても、罰則がなければこれを破った者を罰することができません。現行の条例の考え方では、カスハラが刑法でいうところの脅迫、強要、恐喝、暴行・傷害、不退去などに該当した場合は、刑法犯として罰するという考えなります。しかし、条例に反した者を刑法で罰することに違和感はありませんか?刑法に抵触するような(ある意味重大な)犯罪行為を行ったからこそ、それ相応の刑法上の罰則が科される訳であって、刑法の罰則は、カスハラを行なった事への違反による罰則では決してありません。
残念ながら、改正法でも罰則は盛り込まれていません。では、カスハラ行為者を刑法犯として逮捕し罰することは可能なのでしょうか。可能であるのは事実ですが、逮捕に至るまでは犯罪構成要件が関わってきますので、実際には継続的にカスハラ(刑法犯の類)行為を受け、ようやく逮捕という流れが殆どです。この場合、少なくとも複数回のカスハラ行為を我慢し、警察を呼んでも罪に問えるか?という確実性のない対応を強いられることになります。もちろん、物理的な実損害である損壊又は暴行・傷害を受けた場合には別ですが、脅迫や恐喝、強要、などは数回の行為を積み重ね(反復継続性)、記録(証拠)も用意した上でようやく警察に動いてもらえるというケースが殆どです。このような状況において、法令・条例でカスハラ被害者を救済することができるのか疑問であると言わざるを得ません。そもそも、カスハラによる被害により、従業員が心身共に傷を負わないために対策を推進しているのに、「被害」が生じることを前提とした刑法の適用を想定していること自体に矛盾があるのです。
長年に亘りカスハラ(不当要求対応)の現場で人的支援をしている当社からすると、罰則を持たない条例の実効性には疑問以外はありません。本当に労働者を守ることができると考えているのか、注意喚起条例でしかないと言わざるを得ません。
唯一、三重県桑名市で制定されたカスハラ防止条例については罰則を設けており、警告を行なった上でも行為が継続するようであれば、市のホームページに氏名を1年間掲載するというものです。制定に際しては様々な声もあったことと思いますが、氏名公表措置を規定したことは、一定の抑止力にはなりますので賞賛すべきだと思います。もちろん、罰則を設ければすべてが解決する訳ではありませんが、いかにカスハラを防止するか、抑止できるかが問題になりますので、効果を大いに期待したいと思います。
労働施策総合推進法の改正へ
さて、労働施策総合推進法(正式には、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」)ですが、この法律は端的にいうと労働者の職業安定、社会的地位の向上、経済・社会の発展、労働者の完全雇用を目指すために作られた法令で、過去2020年6月にはパワハラ防止対策を講じることが義務付けられましたが、通称パワハラ法とも呼ばれ厚生労働省が主管なだけあり、労働者を守るという点から今後も改正が繰り返されるのではないかと考えられます。同法が今回はカスハラ対策も追加した形になりますので、やはり労働者を守るという視点はブレることなく、6月4日参院本会議で可決・成立されました。施行については、2026年中を目指すという発表がされています。
ただし、条例と違う点は事業主と労働者に対する条項が盛り込まれており、取引先等の法人に対してカスハラを行わない(加害者にならない)ための施策を講じなければならないことが明文化されました。
- 事業者に対して(同法第34条3項)
- 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
- 労働者に対して(同法第34条5項)
- 労働者は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
条文で明文化されている通り、カスハラの加害者にならないよう明文化されたものです。
法令に明文化された経営陣への警鐘
事業主である経営者に対して、明確に条文で規定されている内容として、第34条2項及び3項において、
- 事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めること
- 当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をすること
- 自らも、顧客等言動問題に対する関心と理解を深めること
- 他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない
上記(抜粋)が明文化されていますが、簡単にいうと経営者自身がカスハラを理解し、従業員にも理解させる必要があり、研修などによる教育が必要であること。また、他社の従業員に対する言動(カスハラ)に注意することと明記されており、経営陣自らが対策に取り組む必要があると示唆しています。
したがって、「当社の従業員は、しっかりカスハラについて学んでいますよ」では済まされず、経営者自身もカスハラをしっかりと理解しておく必要があるということになります。
今までは各企業の総務部や人事部、コンプライアンス部などが自発的にカスハラ対策を始めようと計画し役員会にはかるものの、場合により縮小案に修正されたりし、思うように進められないというケースが多く見られましたが、これからは逆に経営陣より「カスハラ対策を進めるように!」という指示が出され、対策案を役員会に提示しても「これでは不十分だ」などという意見が出るようになるような状況になるのではないでしょうか。経営陣自体がカスハラに目を向けざるを得ない状況になるわけですから、真摯な取り組みが必要になります。法令が施行されるから、ようやく腰を上げるのではすでに遅いのですが、それでも企業組織が一体となるためには、経営陣の本気度が上がることは良いことであるといえるのではないでしょうか。
条例では被害を受けない視点がメインだが法令ではBtoB加害禁止も明文化
条例では、基本的には「カスハラ被害防止」が中心に制定されており、特に労働者を守るために未然防止から事後の対応までを明記されていますが、労働施策総合推進法では「加害防止の視点」が追加されています。
当たり前のことですが、自社が優位性を持たないBtoB取引もあれば、逆に自社が優位性を持つ取引もある訳ですから、単純に被害防止だけでは事足りず、立場が違えば加害者になり得るのは当たり前に予想できるものです。“下請け業者”との取引関係がカスハラの温床になっていたため、ここにメスを入れてきたいのです。
本来は、このような企業があるからこそ、自社の商売が成立し収益を得られる訳ですから、そのような取引先を“下請け”という考え方ではなく、自社の商売に協力して頂ける“協力会社”(パートナー)という考え方が必要であり、お互いに“Good Partner”であり続ける思考・努力が必要ということです。また、取引業者の担当者も自身と同じ感情もプライドも持つ人間であることを忘れてはいけません。それぞれには立場がありますし、人格もありますので、相手を思いやり尊重し合うことで、そこには信頼が生まれるものではないでしょうか。このような考え方を、経営陣からすべての従業員に対して厳命し、お互いにGood Partnerであることの重要性を説いて頂きたいと思います。
カスハラ対応マニュアルだけでなく加害者にならないためのガイドラインも必須!
以上説明してきたように、今回の改正労働施策総合推進法ではカスハラ加害防止の視点も導入されましたので、企業等で作成するカスハラ対応マニュアルについては、被害を受けないための対処法はもちろんのこと、カスハラが発生した際の対応法も必要になり、そのような場合にどのように沈静化させるか、どうすればカスハラ行為に対する適切な対応ができるのか、この点をマニュアルに盛り込んでいく必要があります。さらにBtoBにおける加害者にならないためにどのように取引先と付き合う必要があるのか、何をするとカスハラ行為になってしまうのか、加害者にならないための基本的な行動指針を盛り込んでおく必要があります。法人間(BtoB)では、例えば、取引先に注文する製品の納期を強引に短くさせるため、できなければ他社と取引を行なうなどと無理強いすることや、自社の飲み会に取引先の女性社員を強引に参加させる、接待の強要などは昔からよくある話ですが、。断ると取引できなくなることを暗に示すような行為、すなわち取引先に対して自社の優位性を示して無理強いする行為は、今後はBtoBにおけるカスハラ加害となり得るのです。
もちろん、時には友好関係を築くためにゴルフや飲み会を行なうような機会もあると思います、そのような場合には、相手方との立場の違いを利用して、強制的(暗黙の了解を含む)に支払いを相手に持たせるような行為は厳禁であることなど、ガイドラインとして策定し、こちらもしっかりと役員や従業員に教育しておく必要があります。
たかだか数百円のコーヒー代でも、それが常態化の始まりとなり、取引先と飲食店に入る際には、出してもらうのが当たり前という感覚になり、そのうちに当然に支払わせる金額が大きくなっていくものです。また、そのように借りを作ってしまうと、便宜を図らなくてはならない状態に陥る場合もあり、正常な取引関係が成立しなくなるようなことも出てくるのです。昭和の時代にはこのようなことが当たり前のようにあったことと思いますが、時は令和の時代で様々な法令・条例で制約を受ける時代であることを忘れてはなりませんし、セクハラ・パワハラ同様に、昭和時代の古い考え方はもはや通用しないことを認識しなけれななりません。そのような事を続けると企業の体質を疑われ、どこの企業も取引をしてくれないという状況に陥ることもあり得ます。どこも取引をしてくれなければ、自ずとその企業の未来は危ういものです。だから、前述の“Good Partner”であり続ける必要があるのです。
おわりに
今、カスタマー・ハラスメントは行政も動くほどの社会問題になっており、各企業は本気で対策を行なわなければならない状況にあること理解して欲しいのです。また、法令・条例が施行されたから慌てて対策を講じるものではなく、自社の従業員を守るのは会社(経営陣)であり、従業員同士になりますので、もっと能動的に、もっと本気で進めることが重要です。
カスハラ被害防止対策、カスハラへの対応、カスハラ加害者にならないための対策。これらは時間が多少かかるものですが、従業員を守るためには完遂すべき企業の責務と認識してください。我々、エス・ピー・ネットワークは、現場の苦労や痛みを知る企業として、これからもカスハラ対策を推し進める企業を全力で応援し、全力で支援してまいります。それが、企業危機管理を実践するエス・ピー・ネットワークの使命であると考えてます。


