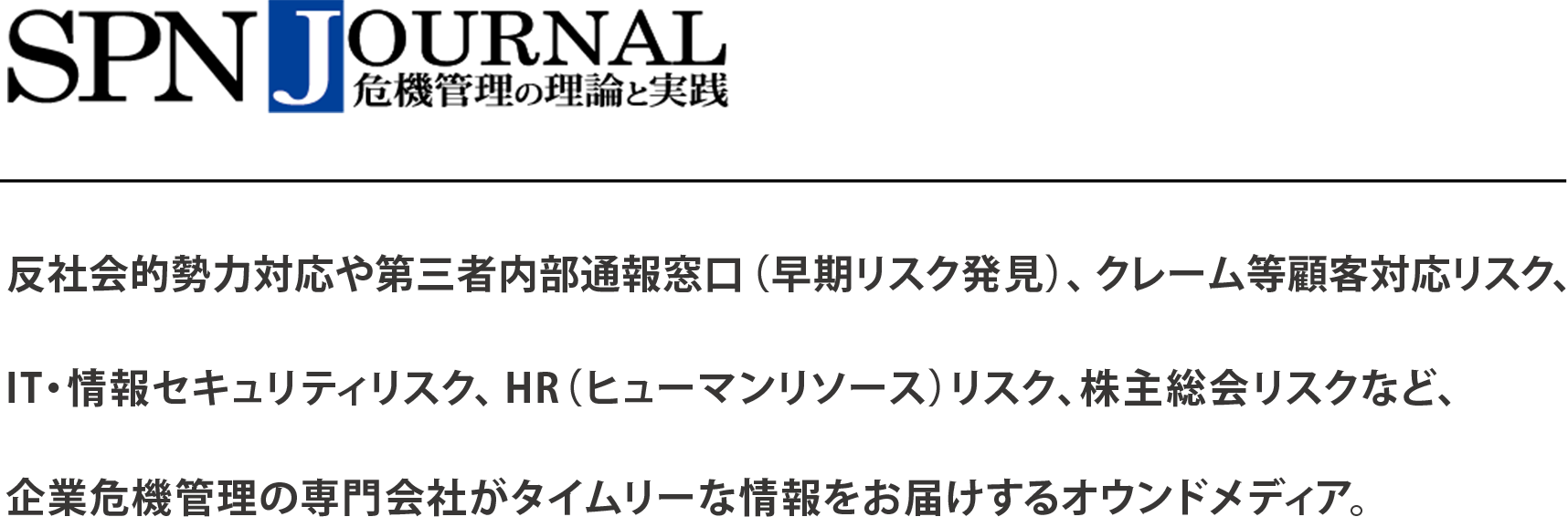記事一覧
-

HRリスクマネジメント トピックス
「もうすぐ年度末なのに…相次ぐ退職希望者」SPNの森 動物たちが語るHRリスクマネジメント相談室
2026.01.27 -

危機管理トピックス
AML・CFTに関するガイドライン一部改正案の公表/月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料/令和7年版 消防白書 概要版
2026.01.26 -

クレーム対応・カスタマーハラスメント対策トピックス
もう一つのカスハラ対策に向けて
2026.01.20 -

危機管理トピックス
人身取引対策推進会議/令和12年度までの社会資本整備・交通政策の羅針盤となる計画を策定/国土交通省南海トラフ巨大地震対策計画」を改定
2026.01.19 -

暴排トピックス
トクリュウ「闇のエコシステム」を破壊せよ~世界でも類を見ない「架空名義口座」導入に期待
2026.01.14 -

危機管理トピックス
金融サービスを悪用したマネー・ローンダリングへの対策に関する報告書/自衛隊・防衛問題に関する世論調査(速報)/eLTAXを装ったメールやSMS等に対する注意喚起
2026.01.13 -

危機管理トピックス
【年末年始に公表された情報まとめ】金融庁・警察庁・経済産業省・法務省
2026.01.06 -

危機管理トピックス
【年末年始に公表された情報まとめ】消費者庁・国民生活センター・総務省・国家サイバー統括室
2026.01.06 -

危機管理トピックス
【年末年始に公表された情報まとめ】内閣官房・内閣府・厚生労働省・首相官邸
2026.01.06 -

危機管理トピックス
【年末年始に公表された情報まとめ】国土交通省・気象庁・復興庁
2026.01.06
30秒で読める危機管理コラム
危機管理のプロの視点から時事ニュースを考察しました。
01月26日号
若者などが闇バイトに加担する流れを食い止めたい
首都圏における闇バイト強盗の首謀者4人の摘発に絡み、闇バイトに応募し、一連の事件で逮捕された実行役は全部で38人、実際に報酬を得ていたのはそのうちわずか6人で、取り分は最大で数万円だったという。「高収入」などとうたう闇バイトに応募しても「割に合わない」実態が示された形だ。また、警察庁は、闇バイトの応募者やその家族に対する保護措置が1年ほどで544件にのぼったと発表。応募者は7割超が男性で、年代別では20代が半数近く、10代が4分の1を占めた。闇バイトの内容は「口座・携帯売買」「受け子・出し子・かけ子」「運び屋」「窃盗・強盗」などが多く、「かけ子」は大半がカンボジアなど海外への渡航を求められていた。なお、「知人からの声掛け」がきっかけとなるケースが増えており、より「届けるべき者に届く」施策が求められる。(芳賀)
役員向けカスハラ対策研修 準備はOK?
厚生労働省労働政策審議会の分科会は20日、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策に関し指針案を取りまとめ、大臣も妥当と答申。予定どおり10月1日施行で動く。指針では「契約金額の著しい減額の要求」「同様の質問を執拗に繰り返す」などカスハラ言動を例示し、対応を促す。体制構築は経営陣のリーダーシップのもと、労働者を保護する方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知する必要性も明記。指針を踏まえると役員向け研修の開催が必須といえ、また内容についても、改正法の目的が労働者に対する各種ハラスメントの被害防止であることを考えれば、カスハラのみならず、労務、顧客対応のリスク管理、コンプライアンスまで広げて受講できる構成を推奨したい。「カスハラ対策もコンプライアンスも経営トップから」10月までの予定を再確認すべし。(宮本)
▼厚生労働省 第89回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
▼News Release『クレーム対応の「超」基本エッセンス 新訂第3版 -カスタマーハラスメント対策7つの柱と顧客対応指針5ヶ条-』を出版 株式会社エス・ピー・ネットワーク
▼もう一つのカスハラ対策に向けて クレーム対応・カスタマーハラスメント対策トピックス 株式会社エス・ピー・ネットワーク
総選挙を無駄にしないためには…
予算審議が犠牲にされることも含め、大義なき解散総選挙が取り行われる。与党の自民・維新連合からは「TM特別報告」に多くの記載がある旧統一教会との関係につき、全く説明責任が果たされていない。一方、立憲と公明が合体された「中道改革連合」は公明の主導であり、創価学会が強力な支持母体であることに変わりはない。また対外的には形の上では、与党の親米(拝米)路線と「中革」の親中(媚中)路線の対立とはなっているが、実質的には両者が入り混じっている。トランプ大統領が強引な新帝国主義的政策を推し進めている現在こそが、実は日米地位協定に基づく日米合同委員会などを改定して、真の日本ファーストを実現するまたとないチャンスである。この場合の日本ファーストとは反米でも反中でもないことを国民も国会議員の多くも認識できているか。(石原)
能登半島地震対応検討報告書を読む
2年前の1月1日に発生した能登半島地震の対応検証報告書が、石川県から公表されている。まずは誠実に報告書を公表した石川県に敬意を表したい。一方で、初動対応については課題が多かったことが分かる。まず災害時の組織体制としては「組織横断チームは編成されていたが、危機管理監室に情報を集約する意識や体制となっておらず、連携に支障が発生した」とのこと。災害対応の第一歩は一元化された情報収集だ。通常の業務の延長線上で情報を集約しようとすると対応が後手に回る。もっと基本的なところでは「執務スペースの不足」が挙げられている。災害対応要員が1つのフロアで業務をすることは、情報共有の点でも組織の一体感を醸成するためにも非常に重要だ。企業BCPにも活用できる教訓が多く記されているので、担当者はぜひご一読していただきたい。(大越)
猫も人も?いなくなって気付きがちな「よい仕事」
久しぶりにかつて野良猫(地域猫?)が多くいた公園に行ってみた。高齢猫ばかりで年数も経っている。公園内や周囲の植込みをのぞいたが、猫はいない。「みんな保護されていたらいいね」と家族と話しながら歩いていくと、前方の植込みでガサガサと音。猫?と思って見ると、そこにいたのは大きなネズミ!休日の昼間、子供用の遊具もある公園に堂々と姿を見せるほど、ここに敵はいないのだろう。子供も近寄らず、公園として用を成さなくなっている。野良猫は疎ましがられ、保護されたり去勢されたりでいなくなっていく。しかし猫は案外よい仕事をしていたのでは?人間も同じかもしれない。人員削減や合理化によって、かつて存在した「よい仕事」に気付くこともあろう。何かをなくせば、何か問題が発生することはよくあるもの。注意深い観察と対処が必要だ。(吉原)
厚生労働省がカスハラや就活等セクハラに関する政令案・省令案・指針案を公表!
カスハラや就活等セクハラに関する政令案・省令案・指針案について、今月20日、厚生労働大臣から労働政策審議会に対して、意見を求めた。今後、労働政策審議会が意見を述べれば、内容はもう決まりと言っていいだろう。こうして、企業等の組織が講じなければならない対策の内容がほぼ具体化されたわけだが、いざ実行に移すとなると簡単ではないと考えられる。カスハラも就活等セクハラも、現場の実態(地域性、業務の内容、採用活動の状況等)に応じて、方針や対策の内容が大きく左右されると考えられるからだ。「ひな型」を使って済ませられるようなものではないのなら、それだけ準備に時間がかかるはずだ。もう厚生労働省は案を提示した。改正法の施行日は10月1日となる予定だ。あまり準備時間が残されていないと考え、早急な対応をお勧めしたい。(安藤(未))
▼厚生労働省「第89回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」
▼読売新聞『「大声で威圧」「土下座強要」はカスハラ…厚労省が対策指針案、該当例を明示』(2026/1/21 6:47)