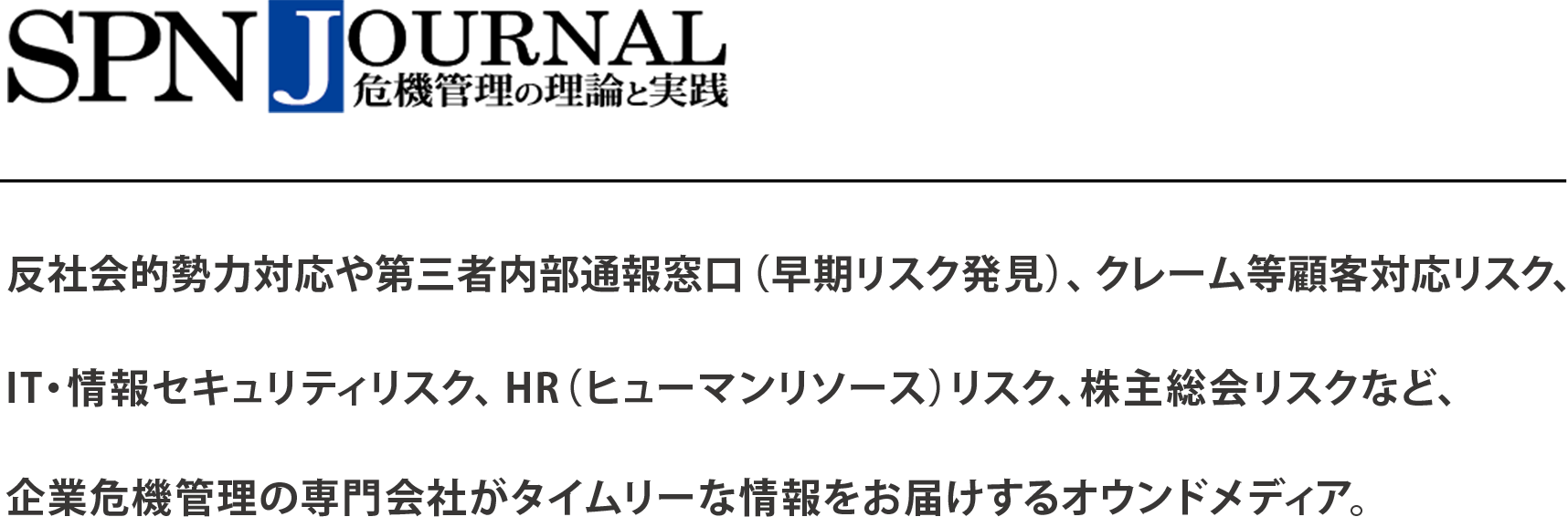記事一覧
-

専門家の集まるBCPカフェ
意外と知らない津波の恐ろしさ~知る・備える・行動する~
2026.02.25 -

危機管理トピックス
有価証券報告書の定時株主総会前の開示/第18回 国土強靱化推進会議/第1回 AI技術の利用と消費者問題に関する専門調査会
2026.02.24 -

企業不祥事・緊急事態対応トピックス
企業不祥事対応 対応方針の策定とリスク評価の手法
2026.02.16 -

危機管理トピックス
令和7年の犯罪情勢/特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等(暫定値)/労働力調査令和7年平均結果要約
2026.02.16 -

暴排トピックス
武器を磨くことで道は拓ける~トクリュウ壊滅に向けて
2026.02.09 -

危機管理トピックス
サイバーセキュリティ月間における取組/ニパウイルス感染症のリスク評価等について/第30回防災まちづくり大賞
2026.02.09 -

SPNの眼
2026年12月施行の改正公益通報者保護法の概要および実務上の留意点について
2026.02.03 -

危機管理トピックス
行政相談における「業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談」への対応について/職場における熱中症防止対策に係る検討会/オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方
2026.02.02 -

HRリスクマネジメント トピックス
「もうすぐ年度末なのに…相次ぐ退職希望者」SPNの森 動物たちが語るHRリスクマネジメント相談室
2026.01.27 -

危機管理トピックス
AML・CFTに関するガイドライン一部改正案の公表/月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料/令和7年版 消防白書 概要版
2026.01.26
30秒で読める危機管理コラム
危機管理のプロの視点から時事ニュースを考察しました。
02月24日号
SNS依存を招く「仕組み」にメスを入れよ
米国では「通信品位法230条」によって、第三者の投稿内容を巡るSNS事業者の責任は原則免除されているが、SNSの投稿内容ではなく、「アプリの仕組みによる中毒性」が争点となった裁判が注目されている。アプリの設計自体に問題があるとする今回の訴訟は、全米で数千件に上る類似訴訟の行方に影響を与える可能性がある。そもそも青少年に悪影響を及ぼすのは特定の投稿内容ではなく、SNS依存に陥る仕組みそのものだ。それは薬物依存やギャンブル依存などと同様の構図だろう。原告は、メタなどは依存を引き起こすと認識しながら、アクセス数や収益を稼ぐために意図的に設計したと主張する。メタのこれまでの行儀の悪さからみれば一定の説得力がある。裁判の結果にかかわらず、子供に悪影響が及ぶ巨大なリスクを認識したうえでの不作為は看過されるべきではない。(芳賀)
エレベーター内の防災グッズをチェックしておこう
東京スカイツリーで22日、エレベーター閉じ込め事案が発生。子ども2人を含む男女計20人が約5時間半にわたって閉じ込められた。全員無事救出されけが人や体調不良者も出なかったというが、その原因究明には時間がかかっており、3日経過した本日24日時点でも再開のめどはたっていない。東京都の首都直下地震被害想定では、最大で2万2426台のエレベーター閉じ込め事案が発生するとしており、救出には数時間から数日かかる場合もあるとする。エレベーター閉じ込めにあった場合に最も有効なのは、やはり「防災チェア」などでエレベーター内に防災グッズをあらかじめ配備しておくことだ。港区では設置を希望する共同住宅すべてに無償で配布する取り組みが始まっている。自分が暮らす集合住宅や会社のエレベーターも、再度チェックしておきたい。(大越)
「謝れ!」と言うのも、悪くもないのに謝るのも「おかしい」と思うから…
夕飯は鍋、あとは白菜を買うだけだったが…グリーンピースの値下げ札に心を奪われた。安い!やっぱり豆ご飯にする?冷蔵庫の食材をもとにメニューを再構成し、グリーンピースをカゴへ。ところがレジで…倍以上の値段。レジの人に「値段が違いませんか?」と言うと、別の店員と何やら話し、しばらくして出た言葉は「値札が違っていました。どうされますか?」だった。反射的に「すみません、今日はやめておきます」と他のものだけ会計を済ませたものの…自分が発した「すみません」にもやもやする。レジの人のミスではないだろうし、ミスは誰にでもある。ここでキレるような人間にはなりたくない。だが謝るべきでないときに謝るような人間でもいたくない。「私が謝るのはおかしいですよね」とつぶやき店を出た。白菜は他店で安く買えたので良しとしよう!(吉原)
がんの早期発見とともに、どう付き合っていくか~LUNA SEAの真矢氏に哀悼の意を表して~
2月17日、LUNA SEAのドラマー、真矢氏が亡くなった。心より哀悼の意を表したい。真矢氏は大腸がんと脳腫瘍で手術や治療を続けてきたものの、56歳の若さで亡くなったそうだ。厚生労働省「2024年の人口動態統計(確定数)」によると、がんによる死亡者数は、約38万人で、全死亡者数の23.9%だ。がんは1981年から死因の第1位が続いている。大腸がんは2024年のがんの死亡者数で見ると、女性の死因の第一位だ。同省の「国民生活基礎調査」によると、通院しながら働いている人は、2,326万人に上り、がんや脳卒中など病気は様々だ。昨年6月に改正労働施策総合推進法が公布され、治療と仕事の両立支援が事業主の努力義務に加わったが、これは将来的に義務化される布石の可能性がある。社会全体として、がんの早期発見とともに、どう付き合っていくかを考えていくべきだろう。(安藤(未))
▼LUNA SEA「皆様へ」(2026/2/23)
▼厚生労働省「人口動態調査」
▼厚生労働省「国民生活基礎調査」
▼厚生労働省「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」